国民健康保険税について
国民健康保険税の納税義務者について
国民健康保険税は世帯単位で合算され、国民健康保険の世帯主(注釈:擬制世帯主を含む)に納めていただくことになります。
注釈:擬制世帯主…世帯主が国保の加入者でない場合でも家族の中に国保の加入者がいる場合、国保税を納める義務は世帯主にあります。この国保の加入者ではない世帯主を擬制世帯主といいます。
国民健康保険税算定について
国民健康保険税の中身は、3つの区分に分かれています。
- 基礎課税分(医療分)・・・・・・・・皆さんがお医者さんにかかられた時の保険者支払い分に使用されます。
- 後期高齢者支援金等分(支援金分)・・・平成20年4月より開始された長寿医療制度(後期高齢者医療制度)を支援するために使用されます。
- 介護納付金分(介護分)・・・・・・・40歳以上64歳までの方は介護分を、医療分及び支援金分と一緒に賦課させていただいています。
そのため、年齢によって、国民健康保険税は、下の表のように納め方が異なります。
- 40歳までの方 医療分+支援金分
- 40歳から64歳までの方 医療分+支援金分+介護分
- 65歳以上の方 医療分+支援金分
注釈:65歳以上の方の介護分は、別途、介護保険料として納めていただいています。担当課は、介護保険課です。
下記の計算式は、年税額の計算方法です。
医療分、支援金分、介護分はそれぞれ、所得割+均等割+平等割の合計金額となります。
所得割+均等割+平等割の合計金額が最高限度額を超えた場合は、最高限度額が年税額となります。
年度の途中での加入・喪失の方は、月割計算で計算されます。
令和6年度国民健康保険税算定の計算式(年税額)
- 医療分(基礎課税分)
区分・計算式
所得割 前年中の総所得から基礎控除(※)後の金額 × 7.8%
均等割 被保険者人数 × 27,700円
平等割 1世帯 × 19,200円
最高限度額 650,000円 - 支援金分(後期高齢者支援金等分)
所得割 前年中の総所得から基礎控除(※)後の金額 × 3.2%
均等割 被保険者人数 × 10,800円
平等割 1世帯 × 7,500円
最高限度額 240,000円 - 介護分(介護納付金分)
所得割 前年中の総所得から基礎控除(※)後の金額 × 2.7%
均等割 被保険者人数 × 11,200円
平等割 1世帯 × 5,700円
最高限度額 170,000円
(※) 基礎控除の額は、前年中の合計所得金額(以下「合計所得金額」)が2,400万円以下の場合は43万円、合計所得が2,400万円を超え2,450万円以下の場合は29万円、合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下の場合は15万円、合計所得金額が2,500万円を超える場合は0円です。
- 年度の途中で40歳になった方はその月から介護分が加算されます。
- 年度の途中で65歳になる方はその前月までの介護分を計算します。
- 年度の途中で75歳になる方はその前月までの分を計算します。
- 未就学児(平成30年4月2日以後生まれ)の被保険者に係る医療分及び支援金分の均等割は、2分の1が減額されます。
計算上の注意点
- 令和6年度とは、令和6年4月1日~令和7年3月31日です。
- 前年中の総所得とは、令和6年度市町村民税の総合課税分+分離課税分の所得金額(退職所得は除く)の合算額(令和5年中の所得)をいいます。
納付方法について
大きく分けて、2つの納付方法(普通徴収、特別徴収)があります。普通徴収には、自主納付と口座引き落としの2つの方法があります。
特別徴収と普通徴収は併用して納付いただく場合があります。納付方法が異なっても、国民健康保険税の合計金額は変わりません。
- 普通徴収
1)自主納付(納付書を使って金融機関やコンビニエンスストアの窓口で、またはご自宅等からスマートフォン決済でお支払いいただく方法)
2)口座引き落とし(引き落とし口座の申請に基づき、その口座から納期限日にお引き落としさせていただく方法) - 特別徴収
3)年金からの特別徴収(一定の条件を満たした方(下記に条件を記載)については、自動的に年金から天引きとなります。ただし、一定の条件を満たし、普通徴収申請書の提出があった方については、口座引き落としに変更することができます。)
注釈:特別徴収から普通徴収(口座引き落とし)へ変更される場合、社会保険料控除の取扱いが異なるため、所得税や住民税が変わる場合があります。
特別徴収になる条件とは
下の1~5の条件を全て満たした世帯のみ、特別徴収の対象となります。対象となりましたら、国民健康保険の世帯主の年金から特別徴収をさせていただきます。ただし、特別徴収されないこともあります。
- 国民健康保険被保険者が65歳以上75歳未満のみで構成された世帯(65歳未満の方と一緒に加入いただいている世帯は、対象外となります)
- 国民健康保険の世帯主が、国民健康保険被保険者(擬制世帯主の場合は、対象外となります)
- 国民健康保険の世帯主が、年額18万円以上の年金額があること
- 国民健康保険の世帯主の介護保険料が、年金から特別徴収されていること
- 国民健康保険の世帯主の介護保険料+国民健康保険税の合計金額が、年金額の2分の1以下。(年金額が年度途中で減額になった場合は、年金額の2分の1以上でも特別徴収が引き続き行われる場合があります)
災害その他の特別な事情がある方で、特別徴収対象外になる世帯があります。
75歳のお誕生日を迎えられる方へ
75歳のお誕生日を迎えられる方は、誕生日から後期高齢者医療制度に加入となります。保険料の請求は誕生日の属する月分から、後期高齢者医療制度からの請求となります。国民健康保険税は、その前月分までの月割計算になります。
保険税は納期内に納付してください
保険税を滞納すると
- 納税義務者(擬制世帯主を含む)は、督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。
- 保険証の有効期限が短くなり(短期被保険者証の交付)、発行の都度、市役所に来庁していただくようになります。
- 国民健康保険の給付(療養費・高額療養費・葬祭費など)を受ける場合は、その給付の全部又は一部を差し止め、滞納保険税にあてることになります。
- 保険証を返していただき、被保険者資格証明書を交付します。この時、特別療養費として支給し、全額滞納保険税にあてることになります。
※納付が困難な場合は、滞納のままにせず、早めに税務課収納係又は保険年金課国民健康保険係までご相談ください。
国民健康保険税の軽減、減免等について
1.非自発的失業者に対する軽減措置について
リストラや倒産など非自発的な理由により離職を余儀なくされ、下記(ア)(イ)(ウ)全てに該当する人は、申請により保険税の軽減(該当者の給与所得を100分の30として算定)が受けられます。ただし、給与所得以外(事業所得・不動産所得・年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得については通常の所得額を用います。
(ア)平成21年3月31日以降に勤務先を離職していること。
(イ)離職日時点で65歳未満であること。
(ウ)「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが、「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当し、失業給付を受ける方。
※「雇用保険特例受給資格者証」、「雇用保険高年齢受給資格者証」の場合は対象となりません。
※保険税の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
【申請に必要なもの】
・対象の方の国民健康保険被保険者証(既に国保に加入されている場合)
・対象の方の「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」(ハローワークで交付されます)
2.後期高齢者医療制度創設に伴う、平等割軽減について
後期高齢者医療制度の被保険者となったことで、国民健康保険の資格を喪失し、引き続き同一世帯に属する人(国保の世帯主であった場合は、その後も継続して国保の世帯主である人)のことを旧国保被保険者といいます。この旧国保被保険者と同一世帯であって、国民健康保険に加入している人が一人になった場合、その世帯(特定世帯という)において5年間、医療分・支援金分の平等割の2分の1を軽減します。また、その後3年間(特定継続世帯という)は4分の1を軽減します。また、「3.法定軽減について」に該当した場合は、さらにその軽減が受けられます。
※軽減判定日は、令和6年4月1日、又は、旧国保被保険者資格取得日となります。(世帯主が変わらない限り令和6年度の判定日は変わりません)
3.法定軽減について
国民健康保険税の法定軽減(均等割額、平等割のそれぞれ7割、5割、2割)は、国民健康保険の世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者と旧国保被保険者の軽減判定所得の合計が軽減判定基準額以下である世帯に適用されます。ただし、所得の申告がない場合、軽減は適用されません。
●軽減基準について(軽減判定所得は、所得割算定の「前年中の総所得金額」とは異なります)
軽減判定所得とは、令和6年度市町村民税の総合課税分+分離課税分の所得金額(退職所得は除く)の合算額(令和5年中の所得)となります。ただし、下記(1)(2)について扱いが異なります。
(1)長期譲渡所得について、特別控除の適用はされません。また、事業主の事業専従者控除は無いものと考えます。(専従者給与収入も無いものとします)
(2)昭和34年1月1日以前に生まれた方については、年金からのみ特別控除150,000円があります。
軽減判定日は、令和6年4月1日、又は、新規資格取得日となります。(世帯主が変わらない限り令和6年度の判定日は変わりません)
世帯の軽減判定所得が、下記の軽減判定基準額以下だった場合、軽減が適用されます。
軽減・軽減判定基準額
・7割軽減 430,000円+(年金・給与所得者の数-1)×10万円
・5割軽減 430,000円+(年金・給与所得者の数-1)×10万円+(被保険者数+旧国保被保険者数)×295,000円
・2割軽減 430,000円+(年金・給与所得者の数-1)×10万円+(被保険者数+旧国保被保険者数)×545,000円
4.後期高齢者医療制度創設に伴う、被扶養者であった者の国民健康保険税の減額について
国民健康保険の被保険者の資格を取得した日において65歳以上であり、かつ、国民健康保険の資格を取得した日の前日において、健康保険・共済組合・船員保険(任意継続含む)の被保険者であった人(後期高齢者医療制度に移った人)の被扶養者であった人を旧被扶養者といいます。この旧被扶養者の国民健康保険税について、当分の間、所得割の全額を減免し、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、均等割を半額になるよう減免します。また、旧被扶養者のみで構成されている世帯の場合、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、平等割についても半額になるよう減免します。ただし、均等割・平等割が既に「国民健康保険税の法定軽減や減免」を適用する前の半額以下になっている場合、均等割又は平等割の減免は適用されません。
※旧被扶養者であった事を証明できる証明書を添えて申請が必要となります。一度申請すると、2年目以降は自動継続されます。
※国民健康保険組合、国民健康保険の被扶養者であった人は除きます。
5.産前産後期間の国民健康保険税の免除について
出産する国民健康保険被保険者にかかる産前産後期間の国民健康保険税の免除制度が令和6年1月から開始しました。詳しくはこちらをご覧ください。
6.条例減免について
「橋本市国民健康保険税の減免に関する規則」により、次にあてはまる世帯は申請により保険税の減免ができる場合がありますので、国民健康保険係の窓口までお問合せ下さい。
前年中に所得があったが、やむをえない理由により失業・廃業・休業となり所得が激減した場合、やむをえず破産となった場合、債務返済のため居住財産を譲渡した場合、災害や盗難により住宅・家財・資産に重大な損害を受けた場合、貧困により生活のため公私の扶助を受ける場合。
所得の申告について
「住民税の申告」をされていない世帯は、「国民健康保険税に関する所得申告書」の提出が必要となります。
また、前年中に収入がなかったり、障がい年金や遺族年金、老齢福祉年金など非課税所得のみの方についても、「住民税の申告」又は、「国民健康保険税に関する所得申告書」の提出などで、所得申告が必要となります。
所得の申告がない場合は、軽減は適用できません。
国民健康保険税の変更点について
令和5年度から令和6年度の変更点
1.国民健康保険税の税率を改正させていただきました。
基礎課税分(医療分)の所得割・・・7.9%から7.8%
基礎課税分(医療分)の均等割・・・28,500円から27,700円
基礎課税分(医療分)の平等割・・・21,100円から19,200円
後期高齢者支援金等分(支援金分)の所得割・・・2.6%から3.2%
後期高齢者支援金等分(支援金分)の均等割・・・9,700円から10,800円
後期高齢者支援金等分(支援金分)の平等割・・・7,100円から7,500円
介護納付金分(介護分)の所得割・・・2.3%から2.7%
介護納付金分(介護分)の均等割・・・10,400円から11,200円
介護納付金分(介護分)の平等割・・・5,500円から5,700円
2.国民健康保険税最高限度額を改正させていただきました。
後期高齢者支援金等分(支援金分)・・・220,000円から240,000円
3.法定軽減の対象が拡大されました。
【5割軽減】対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずる金額が29万円から29.5万円に引き上げられました。
【2割軽減】対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずる金額が53.5万円から54.5万円に引き上げられました。
令和4年度から令和5年度の変更点
1.国民健康保険税の税率を改正させていただきました。
基礎課税分(医療分)の所得割・・・7.4%から7.9%
基礎課税分(医療分)の均等割・・・26,900円から28,500円
基礎課税分(医療分)の平等割・・・21,300円から21,100円
後期高齢者支援金等分(支援金分)の所得割・・・2.2%から2.6%
後期高齢者支援金等分(支援金分)の均等割・・・9,200円から9,700円
後期高齢者支援金等分(支援金分)の平等割・・・7,200円から7,100円
介護納付金分(介護分)の所得割・・・2.1%から2.3%
介護納付金分(介護分)の均等割・・・9,800円から10,400円
介護納付金分(介護分)の平等割・・・5,300円から5,500円
2.国民健康保険税最高限度額を改正させていただきました。
後期高齢者支援金等分(支援金分)・・・200,000円から220,000円
3.法定軽減の対象が拡大されました。
【5割軽減】対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずる金額が28.5万円から29万円に引き上げられました。
【2割軽減】対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずる金額が52万円から53.5万円に引き上げられました。
令和3年度から令和4年度の変更点
1.国民健康保険税の税率を改正させていただきました。
基礎課税分(医療分)の所得割・・・6.9%から7.4%
基礎課税分(医療分)の均等割・・・24,900円から26,900円
基礎課税分(医療分)の平等割・・・21,200円から21,300円
後期高齢者支援金等分(支援金分)の所得割・・・2.1%から2.2%
後期高齢者支援金等分(支援金分)の均等割・・・9,300円から9,200円
後期高齢者支援金等分(支援金分)の平等割・・・7,600円から7,200円
介護納付金分(介護分)の所得割・・・2.0%から2.1%
介護納付金分(介護分)の均等割・・・9,600円から9,800円
介護納付金分(介護分)の平等割・・・5,400円から5,300円
2.国民健康保険税最高限度額を改正させていただきました。
基礎課税分(医療分)・・・630,000円から650,000円
後期高齢者支援金等分(支援金分)・・・190,000円から200,000円
3.未就学児の均等割が軽減されるようになりました。
国民健康保険法施行令の改正により、未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)に係る医療分及び支援金分の均等割の額(低所得者世帯に係る法定軽減が適用される場合は、その軽減後の均等割の額)の2分の1が軽減されるようになりました。




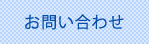
更新日:2024年04月01日