後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、平成20年4月からはじまった全国一律の医療制度です。
都道府県単位で「後期高齢者医療広域連合」が制度を運営することとなります。
和歌山県の場合は、『和歌山県後期高齢者医療広域連合』が保険料の決定や医療の給付を行い、橋本市は各種申請の届出の受付や資格確認書等の引渡し、保険料の徴収などを行います。
被保険者は・・・
原則75歳以上(一定の障害のある方で広域連合の認定を受けた65歳以上75歳未満)の方が被保険者(加入者)となります。
医療機関を受診する際は・・・
病気やけがの治療などで医療機関を受診されるときは、マイナ保険証または資格確認書を窓口で提示してください。
窓口で支払う一部負担金の割合は、資格確認書に記載されています。
保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方
受診の際に「限度額情報の表示」に同意することで自己負担限度額が適用され、医療費や入院時食事代の自己負担額が限度額までに抑えられます。
保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちでない方
受診の際に資格確認書を窓口で提示してください。
住民税非課税世帯(低所得者1、2)に該当する場合、限度区分が併記された資格確認書を提示することで、医療費や入院時食事代の自己負担額が限度額までに抑えられます。
現役並み所得者区分の方で住民税課税所得690万円未満(現役並み所得者1、2)に該当する場合、限度区分が併記された資格確認書を提示することで、医療費の自己負担額が限度額までに抑えられます。
住民税非課税世帯および現役並み所得者区分の方で住民税課税所得690万円未満に該当する場合、「資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」の申請を行うと、資格確認書に限度区分が併記されます。
ただし、前年度減額認定証または限度額適用認定証の交付を受けていた方は、再申請しなくても資格確認書に限度区分が併記されます。
| 負担割合 | 該当要件 |
|---|---|
| 3割 |
同一世帯に住民税課税所得額(調整控除適用後)が145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる方。
|
| 2割 |
|
| 1割 |
上記以外の被保険者 |
注釈: 住民税課税所得額は、住民税の通知には「課税標準額」や「課税される所得金額」と表示されている場合があります。
マイナンバーカードの保険証としての利用について(和歌山県後期高齢者医療広域連合ホームページ)
医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)
1か月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、申請することで限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
また、一度申請すると、次回から高額療養費の支給は申請の必要がありません。
外来および入院の際、同一医療機関での同一月内の窓口負担合計額は、保険のきく部分について外来・入院それぞれの自己負担限度額までとなります。
マイナ保険証または限度区分が併記された資格確認書を医療機関の窓口で提示できなかった場合、低所得者1、2に該当する方は一般の所得区分、現役並み所得者に該当する方は課税所得690万円以上の区分でのお支払いとなり、後日、高額療養費として差額が支給されます。
| 所得区分 | 該当要件 |
外来の限度額 (個人ごと) |
外来+入院の限度額 (世帯ごと) |
|---|---|---|---|
| 一般 | 現役並み所得者、低所得者1、2以外の方 |
1万8,000円 (年間上限14万4,000円) |
5万7,600円 (注1) |
| 低所得者2 | 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方) | 8,000円 | 2万4,600円 |
| 低所得者1 |
|
8,000円 |
1万5,000円 |
(注1)過去12か月以内に、外来+入院の高額療養費の支給を3回以上受けている場合は、4回目以降の限度額が4万4,400円となります。
| 該当要件 |
外来の限度額(個人ごと)、外来+入院の限度額(世帯ごと) |
|---|---|
| 現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
25万2,600円+(医療費-84万2,000円)×1パーセント 多数回 14万100円(注2) |
| 現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
16万7,400円+(医療費-55万8,000円)×1パーセント 多数回 9万3,000円(注2) |
| 現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
8万100円+(医療費-26万7,000円)×1パーセント 多数回 4万4,400円(注2) |
(注2)過去12か月以内に、高額療養費の支給を3回以上受けている場合は、4回目以降は「多数回」該当となり、限度額が下がります。
入院したときの食事代(入院時食事療養費)
入院したときの食事代は、所得区分に応じて1食あたりの食費の標準負担額が決められています。
低所得者1、2に該当する方でマイナ保険証をお持ちでない方は、限度区分が併記された資格確認書が必要になりますので、市役所の保険年金課に申請してください。
やむをえず限度区分が併記された資格確認書等の交付が受けられなかった場合は、申請により、現に支払った標準負担額と減額により支払うべき額との差額が支給されます。
| 所得区分 |
食費(1食あたり) |
|---|---|
| 現役並み所得者 | 510円(注1) |
| 一般 | 510円(注1) |
| 低所得者2該当者の90日までの入院 |
240円 |
|
低所得者2該当者の過去12か月で90日を超える入院 (適用には申請が必要です。) |
190円 |
| 低所得者1 | 110円 |
(注1)指定難病の方は300円。平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院していた方で、平成28年4月1日以降引き続き入院している方は260円。
療養病床に入院した場合は、橋本市保険年金課高齢医療係(電話:0736-33-1273)までお問い合わせください。
高額医療・高額介護合算制度
介護サービスの利用料と医療費の自己負担額の合算が高額になったときは、定められた限度額を超えた額が申請により「高額介護合算療養費」として支給されます。
(毎年8月から翌年7月末までの間が対象となります。)
| 所得区分 | 年間の自己負担限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得者3 | 212万円 |
| 現役並み所得者2 | 141万円 |
| 現役並み所得者1 | 67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 低所得者2 | 31万円 |
| 低所得者1 | 19万円 |
保険料
保険料は、被保険者一人ひとりが等しく負担する『均等割額』と被保険者の所得に応じて負担する『所得割額』の合計額になります。保険料率は、2年ごとに見直され、各都道府県後期高齢者医療広域連合が都道府県ごとに決めます。
令和6・7年度の和歌山県の保険料率は、 均等割額が54,428円、所得割率が11.04%になります。
一年間の保険料は、次の計算方法により算出されます。
- 年間保険料額=均等割額(54,428円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額注釈1×11.04%)
注釈1:賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額等から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。
一人当たり年間保険料の限度額は、80万円です。
こんなときは保険料が軽減されます
所得の低い方、被用者保険の被扶養者であった方は、一定の基準により保険料が軽減されます。
所得の低い方の軽減基準(令和7年度)
| 軽減割合 |
被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額 |
軽減後均等割額 |
|---|---|---|
| 7割 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
16,328円 |
| 5割 | 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+(30.5万円×世帯に属する被保険者数)以下 | 27,214円 |
| 2割 | 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+(56万円×世帯に属する被保険者数)以下 | 43,542円 |
注釈1:軽減判定において、65歳以上の公的年金を受給されている方は、公的年金に係る所得から15万円の控除が適用されます。
被用者保険の被扶養者だった方の軽減措置
後期高齢者医療制度に加入する日の前日に被用者保険の被扶養者であった方は、所得割はかかりません。均等割額は資格取得後2年間に限り5割軽減となります。
ただし、低所得により均等割軽減の対象となる方は、軽減割合の高い方(保険料が安い方)が優先されます。
令和6年度までの保険料等については、和歌山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください
保険料について(和歌山県後期高齢者医療広域連合ホームページ)
保険料の納め方
年金から天引きされる特別徴収と納付書等で納める普通徴収の2通りの方法があります。
特別徴収
年金が年額18万円以上の方で、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超えない方が対象となります。
年6回の年金の支給のとき(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に介護保険料とともに年金からあらかじめ天引きされています。
仮徴収と本徴収
年度の前半には保険料がまだ確定していませんので、4月、6月、8月の年金振込時には、前年度の2月の特別徴収額と同じ金額を天引きします。これを仮徴収といいます。
その後、前年度の所得等により年間の保険料を算定し、そこから仮徴収分を差し引いた額を、10月、12月、2月の年金振込時に天引きします。これを本徴収といいます。
- 注釈1:4月から新たに特別徴収が開始となる方は、前年度の年間保険料の約6分の1が一回あたりの仮徴収額となります。3月末に仮徴収額決定通知書を送付します。
- 注釈2:前年度から継続して特別徴収の対象となる方は、仮徴収額通知書の送付はありませんのでご了承ください。
納付方法の変更について
納付方法を特別徴収から口座振替に変更することができます。詳しくは、橋本市保険年金課高齢医療係(電話:0736-33-1273)までお問い合わせください。
普通徴収
年金が年額18万円未満の方、または、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える方などが対象となります。市から送られてくる納付書で、納期限までに市役所や下記の金融機関で納めてください。
・納付書の取扱金融機関
紀陽銀行、南都銀行、和歌山県農業協同組合、きのくに信用金庫、近畿労働金庫、郵便局・ゆうちょ銀行
注釈1:郵便局・ゆうちょ銀行は近畿2府4県のみの取り扱いです。
口座振替で保険料を納付いただけます
口座振替を希望される場合は、保険料の納付書、預金通帳、通帳届出印をお持ちのうえ、金融機関にてお申し込みください。
・口座振替の取扱金融機関
紀陽銀行、南都銀行、関西みらい銀行、和歌山県農業協同組合、三菱UFJ銀行、きのくに信用金庫、近畿労働金庫、郵便局・ゆうちょ銀行
・インターネットでの口座振替のお申込みについて
紀陽銀行および南都銀行の口座からの保険料の振替申込みについて、お手持ちのパソコン、スマートフォン等からウェブ上で手続きできるようになりました。
市役所や金融機関の窓口に出向く必要がなく、口座振替依頼書の記入や押印も不要ですのでぜひご利用ください。
詳しくは下記リンク先『市税・保険料の口座振替お申込はWEBでのお手続きが便利です』でご確認ください。
こんなときは届け出が必要です!
- 被保険者が亡くなられたとき
- 転入・転出されるとき
- 市内で転居されたとき
- 氏名変更などがあったとき
届け出の様式については、和歌山県後期高齢者医療広域連合ホームページからダウンロードすることができます。
各種申請様式ダウンロードページ(和歌山県後期高齢者医療広域連合ホームページ)
委任状については次のページからダウンロードできます
交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によって病気やけがをした場合でも、届け出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。この場合、必ず市役所保険年金課で「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療制度が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
ジェネリック医薬品について
ジェネリック医薬品は、「後発医薬品」とも呼ばれ、新薬(先発医薬品)の独占販売期間が終了した後に販売が許可される医療用医薬品のことをいいます。
ジェネリック医薬品は新薬に比べ、一般的に安価で提供されるため、医療費の節約や医療保険財政の改善につながります。
ジェネリック医薬品についての詳細は、厚生労働省ホームページ、または和歌山県ホームページをご覧ください。
制度については、和歌山県後期高齢者医療広域連合のホームページもご覧ください
電話 073-428-6688(代表)




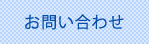
更新日:2025年08月01日