令和6年度食品ロスダイアリー調査結果
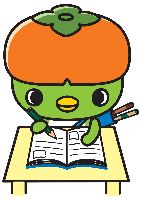
まだ食べられるのに廃棄される食品のことを「食品ロス」と言います。「食品ロス」は、大切な資源や環境に影響を及ぼします。食品ロスを減らすことが必要です。
橋本市消費生活センターでは、食品ロスを減らす行動のきっかけとしていただくため、家庭から「食品ロス」がどのくらい出ているのかを家族で記録する「食品ロスダイアリー」にチャレンジしていただきました。
チャレンジ世帯数
橋本小学校5年生25世帯
柱本小学校5年生20世帯
城山小学校5年生36世帯、6年生49世帯
隅田小学校6年生29世帯
高野口小学校4年生24世帯
合計 5校、183世帯
実施方法
実施期間
令和6年7月20日から令和6年8月25日の期間内のうちの2週間
調査に使用した食品ロスダイアリー
1週間ごとに
1.未使用のまま捨てた食品
2.調理くず
3.食べ残した食品
【1・2・3】それぞれの種類と重さ(g)を記録していただきました。
食品ロスの発生状況(結果)
1.未使用のまま捨てた食品の重さ(集計) 131,789g
| 【入手方法】 | 集計(件数) | 割合 | 順位 |
| 買った | 655 | 68.1% | 1 |
| もらった | 185 | 19.2% | 2 |
| 作った | 122 | 12.7% | 3 |
| 無記入 | 12 | 除外 |
| 【捨てた理由】 | 集計(件数) | 割合 | 順位 |
| 傷んできた、腐った | 448 | 47.1% | 1 |
| 期限が切れた | 236 | 24.8% | 2 |
| その他 | 128 | 13.4% | 3 |
| 好みでなかった | 98 | 10.3% | 4 |
| あきた | 42 | 4.4% | 5 |
| 無記入 | 10 | 除外 |
| 【捨てたもの】 | 集計(件数) | 割合 | 順位 |
| やさい類 | 417 | 42.7% | 1 |
| 調理済み食品・加工品 | 171 | 17.5% | 2 |
| パン類・ごはん類 | 123 | 12.6% | 3 |
| くだもの類 | 98 | 10.0% | 4 |
| 肉・魚類 | 69 | 7.1% | 5 |
| おかし類 | 60 | 6.1% | 6 |
| その他 | 39 | 4.0% | 7 |
捨てたやさい類はどうやって入手した?
| 【やさい類・入手方法】 | 集計(件数) | 割合 | 順位 |
| 買った | 271 | 65.6% | 1 |
| もらった | 99 | 24.0% | 2 |
| 作った | 43 | 10.4% | 3 |
| 無記入 | 4 | 除外 |
2.調理くずの重さ(集計) 309,535g
3.食べ残した食品の重さ(集計) 100,745g
| 【食べ残した理由】 | 集計(件数) | 割合 | 順位 |
| 作りすぎ・量が多い | 326 | 42.9% | 1 |
| 食べられる部分でなかった | 190 | 25.0% | 2 |
| 放置していて忘れた | 104 | 13.7% | 3 |
| 好みではなかった | 88 | 11.6% | 4 |
| その他 | 52 | 6.8% | 5 |
調査結果(要約)
1.未使用のまま捨てた食品
【入手方法】
「買った」655件(68.1%)、
「もらった」185件(19.2%)が上位だった。
【捨てた理由】
「傷んできた、腐った」448件(47.1%)、
「期限が切れた」236件(24.8%)で、全体の約71.9%を占めていた。
【捨てたもの】
「やさい類」417件(42.7%)、
「調理済み食品・加工品」171件(17.5%)が上位だった。
【捨てたやさいはどうやって入手した?】
「買った」271件(65.6%)、
「もらった」99件(24.0%)となり、
「買った」が最も多かった。
3.食べ残した食品
【食べ残した理由】
「作りすぎ・量が多い」326件(42.9%)、
「食べられる部分ではなかった」190件(25.0%)が上位だった。
食品ロス分類(重量)比較
未使用食品 : 131,789g
調理くず : 309,535g
食べ残し : 100,745g
調査結果(詳細)
小学校5校、183世帯のまとめはコチラ
考察
「未使用食品」・「調理くず」・「食べ残し」はそれぞれ「調理以前」・「調理中」・「食事後」というように、食品ロスが発生するタイミングを示しています。
未使用のまま捨てた理由として、「痛んできた・腐った」「期限が切れた」が多く、必要な分だけ購入するなど工夫することで、未使用のまま捨てる食品の量を削減することができると考えられます。
最も多い「調理くず」は、「調理中」に発生していることが一番の要因と判明しました。食品ロスの少ないレシピやゴミにしない方法(生ごみ堆肥化)を心掛けることで、食品ロス削減の効果を期待できると考えられます。
食べ残しの理由である「作りすぎ・量が多い」は作る人が、「放置していて忘れた」「好みでなかった」は、食べる人が意識することで食品ロスを削減することができます。
食品ロスダイアリー調査を通じての変化
・記録することで、気づかないうちに食品ロスをしていたことがわかった。
・食品をムダに捨てないように、計画的に購入する。
・作りすぎないようにする。ご飯やおかずの量を考える。
など食品ロス削減を意識する世帯が多くみられました。
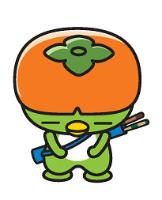
食品ロスダイアリーにチャレンジしてくださった児童のみなさん、ご家族のみなさん、ご協力いただきました各学校の先生方、ありがとうございました。
橋本市 総務部 生活環境課(消費生活センター)
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1165 ファクス:0736-33-1200
問い合わせフォーム




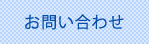
更新日:2024年12月11日