地震に伴う火災にご注意ください!
地震が起きると、火災が発生する危険があります!
平成7年に発生した阪神・淡路大震災では地震により298件もの火災が発生しました。その被害は焼損面積が80万平方メートルを超え、死者6,434人のうち焼死が死因の12.8%を占めるなど、多くの方が火災により亡くなっています。
平成23年東日本大震災においては、本震による火災全111件のうち、原因が特定されたものが108件。そのうち過半数が電気関係の出火でした。
また、平成28年熊本地震では16件の火災が発生し、1人の方がお亡くなりになりました。
地震による火災は、同時に発生することが多く大規模な火災に発展するする可能性があることから、ご家庭においても未然に火災を防ぐことが重要となります。

地震火災の原因
地震による家屋の倒壊や家具の転倒により、ガス管や電気配線が破損したり、ストーブなどの暖房器具に可燃物が接触することにより火災が発生します。
また、地震による停電が復旧した際、スイッチが切れていない電化製品が通電状態となり、火災となる通電火災も多く発生しています。
地震火災を防ぐポイント
事前の対策
- 住まいの耐震性を確保しましょう。
- 家具の転倒防止対策(固定)を行いましょう。
- 感震ブレーカーを設置しましょう。
- ストーブ等の暖房機器の周辺は整理整頓し、可燃物を近くに置かないようにしましょう。
- 住宅用消火器等を設置し使用方法について確認しましょう。
- 住宅用火災警報器を設置しましょう。
地震直後の行動
- 停電中は電気器具のスイッチを切るとともに、電源プラグをコンセントから抜きましょう。避難するときはブレーカーを落としましょう。
- 石油ストーブや石油ファンヒーターからの油漏れの有無を確認しましょう。
- ガス機器、電気器具及び石油器具の使用を再開するときは、機器に破損がないこと、近くに燃えやすいものがないことを確認しましょう。
- 再通電後は、しばらく電気器具に異常がないか注意を払いましょう。(煙、におい)
- 消防団や自主防災組織等へ参加しましょう。
- 地域の防災訓練へ参加するなどし、発災時の対応要領の習熟を図りましょう。

地震火災を防ぐポイント
「地震火災対策きちんと出来ていますか?」 (PDFファイル: 2.0MB)
電気火災対策には、感震ブレーカーが効果的です
地震の時、自動で電気を遮断できる感震ブレーカーをつけましょう (PDFファイル: 273.2KB)
火災予防啓発映像
地震、風水害に伴う通電火災の対策については、総務省消防庁が配信している広報用映像資料をご視聴いただき、参考にしてください。
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
問い合わせフォーム




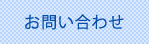
更新日:2025年04月25日