介護保険負担限度額の認定(食費・居住費等の軽減)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院に入所している方や、ショートステイを利用する方は、介護保険が適用される施設サービス費の自己負担分(1割、2割または3割)に加え、実費負担分として食費・居住費(滞在費)、日常生活費が必要となります。
このうち食費と居住費(滞在費)については、一定の低所得要件を満たした方を対象に、所得に応じた限度額を設け、食費と居住費(滞在費)を軽減することができます。なお、軽減を受けるには、申請が必要です。
対象となる方
次の要件すべてに該当する方が対象となります。
(1)本人及び世帯全員(世帯分離している配偶者、内縁も含む)が市町村民税非課税
(2)本人及び配偶者(世帯分離している配偶者、内縁も含む)の預貯金等の資産額が
第1段階 単身の場合:1,000万円以下 夫婦の場合:2,000万円以下
第2段階 単身の場合: 650万円以下 夫婦の場合:1,650万円以下
第3段階(1) 単身の場合: 550万円以下 夫婦の場合:1,550万円以下
第3段階(2) 単身の場合: 500万円以下 夫婦の場合:1,500万円以下
※預貯金等の範囲
・預貯金(普通・定期)
・有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
・金や銀など購入先の銀行等の口座残高により、時価評価額が容易に把握できる貴金属
・投資信託
・現金(タンス預金)
・負債(借入金・住宅ローンなど)
負債については、資産の合計額から控除します。
利用者負担段階と1日あたりの負担限度額
・第1段階 本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者。生活保護受給者
・第2段階 本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課
税年金収入額の合計が80万円以下の方
・第3段階(1) 本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課
税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方
・第3段階(2) 本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課
税年金収入額の合計が120万円超の方
| 利用者 負担段階 |
居住費等の負担限度額(1日あたり) | 食費の負担限度額 (1日あたり) |
||||
| ユニット型個室 | ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | 施設 サービス |
短期入所サービス | |
| 第1段階 | 880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 | 880円 | 550円 | 550円 (480円) |
430円 | 390円 | 600円 |
| 第3段階(1) | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 650円 | 1,000円 |
| 第3段階(2) | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 1,360円 | 1,300円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額になります。
負担限度額認定申請
負担限度額認定の申請方法
○提出書類
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 本人・配偶者名義の預貯金・有価証券・投資信託等の通帳のコピー
- 銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページ
- 申請日の直近2ヶ月分が記載されているページ(直近2ヶ月以内に出入金がない場合、最新の記帳がされているページ)
注1)通帳については必ず記帳してからコピーしてください。
注2)通帳等が複数ある場合は全ての通帳等のコピーを用意してください。利用していな
い口座の通帳でも、解約をされていない利用有効な口座であればコピーの提出が
必要です。
○提出時の注意点
- 申請書のご記入もれがないかご確認ください。申請書に不備がある場合、申請書を返送し、ご記入のうえ再度提出していただくこととなります。その結果、認定が遅れる場合がありますので十分ご注意ください。
- 配偶者がいる方は住所及び世帯の別、内縁に関わらず、配偶者名義の通帳等の写しの提出及び課税状況の記入をしてください。
- 夫婦ともに軽減を受ける方は、夫婦それぞれの申請書に2人分の通帳等の写しを添付してください。
- 預貯金額等の資産が、一定額を超過し、負債(借入金・住宅ローン)がある方については、預貯金額等から負債額を差し引き、一定額以下になる場合は認定を受けられる可能性があります。負債金額等を申請書にご記入のうえ、負債金額が分かる書類(借用証書など)の写しを添付してください。
- 生活保護受給者、境界層措置の方は預貯金等の資産に関する書類の提出、同意書のご記入は不要です。申請書のみご記入いただきご提出ください。
- 第2号被保険者の預貯金等の資産額要件は、単身で1,000万円以下、夫婦の場合で2,000万円以下となります。
○負担限度額認定後の注意点
- 配偶者の有無についての戸籍調査や本人及び配偶者の所得、資産情報の照会を金融機関等に対して行う場合があります。その結果、認定結果が変更となることがあります。
- 上記の照会の結果、認定基準を満たさないことが判明した場合は、給付額の返還に加え、給付額の最大2倍の加算金を徴収することがあります。
負担限度額認定申請書 (Excelファイル: 57.0KB)
負担限度額認定申請書(記入例) (PDFファイル: 515.6KB)
負担限度額が適用されない方で軽減が認められる特例について
市町村民税課税世帯の方は、食費・居住費等の軽減の対象外ですが、夫婦のうち一方が施設に入所することで、残された配偶者の在宅での生計が困難になる場合、次の要件すべてを満たすことで、第3段階(2)の負担軽減を受けることができます(ショートステイは対象外)。
・要件
- 介護保険施設に入所する時点で、世帯(※1)の構成人数が2名以上であること
- 世帯の年間収入(※2)から、施設の年間利用者負担(自己負担、食費、居住費)見込み額を除いた額が、80万円以下であること。
- 世帯(配偶者が別世帯の場合、その配偶者も含む)の預貯金等の合計額が450万円以下であること。
- すべての世帯員が、日常生活のために必要な資産(自宅の土地、建物など)以外に、資産を保有していないこと。
- すべての世帯員が介護保険料を滞納していないこと。
※1 この要件中の世帯とは、施設入所するにあたり世帯を別にする場合は、世帯を分ける
前の状態のことをいいます。
※2 世帯の課税年金収入額に年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所
得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た金額)を加えた
金額のことをいいます。




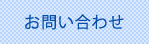
更新日:2024年08月01日