介護予防教室「出張講座」
いきいき健康課では、市内で活動している団体を対象に市職員等が出向き、講座を同一団体に年間3回まで実施しています。
申し込み方法
(テーマ・内容)
下記のとおり
(対象)
会員がおおむね65歳以上の市内で活動している団体
(日時)
原則、ご希望に応じます。(平日の日中、土日)
業務の都合上、ご希望に応じられない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
(費用)
職員の派遣や配布資料等の作成は市で負担します。
ただし、会場の手配やそれにかかる費用は、申し込み者様の負担となります。
(申し込み方法)
日程調整等が必要になりますので、実施希望日の約1か月前までに担当までお申し込みください。
担当:いきいき健康課高齢福祉係
TEL:0736-33-3705
FAX:0736-34-1652
MAIL:ikiiki@city.hashimoto.lg.jp
ロゴフォーム URL:https://logoform.jp/form/dD8K/498042
二次元コード

〇その他
営利、政治活動または宗教活動を目的とする集会等の場合はお受けできません。
テーマ・内容
▶フレイルに関すること
1.フレイルを予防しよう
「フレイル」は心身ともに元気な状態と要介護の状態の中間のことをいいます。
「フレイル」状態になったり、なりそうな方が予防することで元気を回復できたり、要介護の状態を防ぐことができると言われています。
フレイルチェックと簡単な体力測定を実施します。
2.eスポーツ体験会(R7年夏以降)
「eスポーツ」とはゲーム機やパソコンなどの電子機器を使用し、二人以上で競う対人競技です。
ねんりんピック文化交流大会の正式種目となっています。相手の動きを予測して、臨機応変に対応する必要があることから脳トレの効果もあり、脳の活性化や認知機能を向上させることが期待されています。
▶身体に関すること
3.血圧を正しく測ろう
みなさん血圧は測っていますか?血圧は測定方法で数値が大きく変わります。正しい方法で測定して、自分の血圧を知ることが大切です。
4.骨粗しょう症予防
年齢とともに骨がもろくなり、姿勢が悪くなったり、骨折を招くといわれています。
骨量測定を実施し、食生活の見直しや、骨粗しょう症を予防する運動を紹介します。
※測定時に裸足(右足のみ)になる必要があります。
5.熱中症と脱水症(夏季限定)
熱中症は高温多湿な空間で長時間いることにより、体内に熱がこもった状態をさします。
熱中症の理解を深め、対処方法をお伝えします。
6.転倒・尿失禁予防の体操
日常的な体の動きをスムーズに行うためには、筋肉の柔軟性と筋力を高めることが大事です。
正しい型のストレッチと筋力トレーニングを紹介します。高齢者の7割が何らかの「尿の悩み」を抱えています。
体操や生活の工夫で改善する方法を紹介します。
7.口の中の健康管理
口は命の入り口と言われています。
正しいお口の手入れや管理ができていると「糖尿病」や「認知症」、「肺炎」などの病気の予防にもなります。
歯磨きや義歯の手入れの仕方、噛む力をつける体操を実施します。
8.健康な腸の話
腸の健康は体調と大きく関係します。便は健康のバロメーターでもあります。
腸を整えて、心と体の健康を保ちましょう。
▶生活に関すること
9.地域包括支援センターによる相談会
日頃の生活、将来のことなど不安に思っていることはありませんか。
生活支援や介護サービスについて説明、紹介します。
心配事などの相談に応じます。少人数でも気軽にご相談ください。
10.人生会議のすすめ方
人生会議とは、もしもの時のために自分が望む医療やケアについて前もって考え、話し合うことです。最後まで自分らしく生きるために人生会議をしてみませんか。
11.日常生活の工夫・ヒント
リハビリ専門職のみんなでまとめた「橋本市いきいき生活ヒント集」を使って、日常生活でのちょっとした工夫を紹介し、生活に役立つヒントを紹介します。
▶認知症に関すること
12.認知症を知ろう
認知症は脳の病気です。正しく理解し、認知症になっても住み慣れた地域で暮らしていけるよう認知症の症状や対応の方法についてお話します。
脳を活性化させる体操やドリルなども実施します。
▶運動に関すること
13.いきいき百歳体操
「年をとるにしたがって、誰もが体が弱って介護が必要になる」と思っていませんか。「いきいき百歳体操」で体力をつけ、いくつになっても元気でいきいきとした生活を送りましょう。
椅子に座ってDVDを見ながら行います。動作のポイントやコツについて紹介します。一緒に体を動かしてみませんか?
14.体組成測定
機械を使って、身体の水分量や筋肉量、体脂肪を測ります。
フレイル予防には筋肉が大切です。測定結果をもとに、どんなことに取り組めばよいかお伝えします。
※測定時に裸足になる必要があります。
15.ラジオ体操
いつでも、どこでも気軽にできるラジオ体操について正しい動きで安全に行うポイントを紹介します。
ラジオ体操を通して健康づくりに取り組んでみませんか。
▶橋本・伊都在宅医療・介護連携支援センター事業
16.薬の正しい使い方(薬剤師会)
17.感染症対策(薬剤師会)
18.腰痛膝痛予防(理学療法士協会)
▶その他
19.消費生活センター出張講座
20.ヤクルト健康講座
21.関西電気保安協会電気講習会
22.警察による交通安全講習




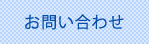
更新日:2025年04月01日