限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について
医療費が高額になると見込まれる場合、医療機関等の窓口で国民健康保険被保険者証(以下、保険証)と限度額適用認定証(非課税世帯の場合、限度額適用・標準負担額減額認定証。以下、認定証)を提示いただくことで、月単位での同一医療機関等で支払う自己負担分の支払いが自己負担限度額までとなります。
また、非課税世帯の方は入院時の食事代の標準負担額が減額となります。
世帯に所得が未申告の方がいる場合、所得要件が一番高い区分での認定となります。
国民健康保険税に滞納がある場合、認定証は交付できず、マイナンバーカードを保険証として利用していただいたとしても、自己負担限度額の適用を受けることはできません。
申請方法
保険年金課窓口、電子窓口で申請が可能です(現在調整中のため、お使いいただけません)
申請により、申請月の初日から(申請した月に国民健康保険に加入した場合は、国民健康保険加入日)から有効な認定証を交付いたします。
電子窓口での申請の場合、普通郵便で世帯主様宛(送付先を指定されている場合は送付先)に送付いたします。お手元に届くまで日数がかかりますのでお急ぎの場合は保険年金課窓口にて申請をお願いします。
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関で、マイナンバーカードを保険証として利用いただいて情報提供に同意いただいた場合や、オンライン資格確認を導入されている医療機関で情報閲覧に同意いただいた場合は、認定証を提示せずとも同一医療機関での支払いは自己負担限度額までとなります。
(厚生労働省)マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク>
保険年金課窓口で申請
【申請可能な方】
・本人か同一世帯の方(別世帯の方は委任状が必要になります)
【お持ちいただくもの】
・申請される方(窓口に来られる方)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・対象の方の国民健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれかお持ちのもの
【受付場所】
・保険年金課国民健康保険係
電子窓口で申請
【申請可能な方】
・本人か同一世帯の方(別世帯の方は委任状を作成の上、窓口か郵送でお手続きをお願いします)
【申請に必要なもの】
・申請される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
【申請方法】
70歳未満の人の自己負担限度額について
自己負担限度額(月額)
| 所得要件 | 区分 | 3回目までの自己負担限度額 |
4回目以降の自己負担限度額 (多数該当) |
|
旧ただし書所得 901万円超 |
ア |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
|
旧ただし書所得 600~901万円以下 |
イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
|
旧ただし書所得 210~600万円以下 |
ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
|
旧ただし書所得 210万円以下 |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※多数該当:過去12か月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額。
※旧ただし書所得=総所得金額等-基礎控除額
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額について
70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方は誕生日の当月)1日からの適用になります。
75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
所得区分が「現役並み3」と「一般」の方は、保険証と高齢受給者証を提示していただくことで、自己負担限度額までの支払いとなり、認定証の申請は不要です。
自己負担限度額(月額)
| 所得要件 | 所得区分 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
| 課税所得690万円以上 | 現役並み3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数該当(4回目以降)140,100円】 |
|
| 課税所得380万円以上690万円未満 | 現役並み2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数該当(4回目以降)93,000円】 |
|
| 課税所得145万円以上380万円未満 | 現役並み1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数該当(4回目以降)44,400円】 |
|
| 課税所得145万円未満 | 一般 |
18,000円 |
57,600円 【多数該当(4回目以降)44,400円】 |
| 住民税非課税世帯 | 低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
|
住民税非課税世帯 (所得が一定以下) |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
※多数該当:過去12か月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額。
入院時の食事代の標準負担額について
入院時の食事代は、1食あたり下記の自己負担となります。
住民税非課税世帯の方と低所得2の区分の方は、90日を超える入院の場合、マイナンバーカードを保険証利用していただいている場合でも、減額を受けるためには限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要となります。
令和7年4月1日から食事標準負担額が変更になります。
令和7年4月1日以降
| 一般(下記以外の人) | 510円 | |
|
住民税非課税世帯(70歳未満) 低所得2(70歳以上75歳未満) |
90日までの入院 | 240円 |
|
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
190円 | |
| 低所得1(70歳以上75歳未満) | 110円 | |
令和7年3月31日まで
| 一般(下記以外の人) | 490円 | |
|
住民税非課税世帯(70歳未満) 低所得2(70歳以上75歳未満) |
90日までの入院 | 230円 |
|
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
180円 | |
| 低所得1(70歳以上75歳未満) | 110円 | |




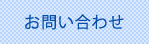
更新日:2025年04月10日