災害に備えた水道水のくみ置きについて
水道水の備蓄は災害対策として有効です
水道水を保存することは、普段からできる災害対策として有効な手段のひとつです。飲料水は人が生きる上で欠かせないものであるため、日常からの備えをお願いします。
また、災害により甚大な被害を受け大規模な断水が発生した場合は、給水車が出動し市民の皆様に飲料水を提供することになりますが、給水の待ち時間や、自宅や避難場所まで水を運ぶことを想像すると、非常に大変な労力を必要とします。ご家庭の中で水道水を用意することは、運搬の苦労がないという点でも緊急時の備えとして有効です。
ふたのある容器に口元まで
清潔で蓋のできる容器を使用し、容器内に空気が残らないように口元いっぱいまで水を入れるようにしてください。
汚染を防止するため、蓋の周囲には手を触れないように、そして、使用時には必ずコップ等に移しかえるようにしてください。ポリタンクを使用する場合も、水の取り出し口が汚れないように十分ご注意ください。
保存容器には使用済みのペットボトルを再利用すると便利ですが、臭いが残っているものは、水に臭いが移るおそれがあるため適しません。
蛇口から直接くみ取る
水道水は消毒のために塩素が加えられています。この塩素によって清潔な状態が保たれているため、保存用には、蛇口から直接容器にくみ取るようにしてください。
浄水器を通した水や沸騰させた水は、塩素による消毒効果が失われているため、保存用には不向きです。
1人3リットル を 3日分
人間が1日の間に必要とする水の量は、「1人3リットル」です。この量を基準に、家族の人数に合わせて3日分程度のくみ置きをご検討ください。
<保存水量の例>
1人暮らしの場合:1人×3リットル×3日= 9リットル
2人家族の場合 :2人×3リットル×3日= 18リットル
3人家族の場合 :3人×3リットル×3日= 27リットル
4人家族の場合 :4人×3リットル×3日= 36リットル
5人家族の場合 :5人×3リットル×3日= 45リットル
保存期間は 3日(常温)・7日(冷蔵)
水道水をくみ置きする場合、保管場所は光が当たらず、涼しい場所に保管してください。凍らない範囲で温度が低いほど長持ちするため、冷蔵庫の中が適しています。
保存期間は、常温で3日・冷蔵で7日が目安です。開封済みのペットボトル飲料(お茶等)を保管するときと同じように、管理するようにしてください。
保存期間を過ぎた水は、洗濯や風呂、草木への水やり等、飲用以外の方法で使用していただくと無駄なく活用することができます。
長期保管は店売りのペットボトル水を活用する
水道水の保存期間は最大でも1週間程度であるため、長期間の保存を検討する場合は、スーパーマーケットやドラッグストア等で買うことができるペットボトル水をご活用ください。
必ずコップを使用する
くみ置きした水を飲むときは、必ずコップ等に移すようにしてください。また、蓋を開けている時間ができるだけ短くなるようにご注意ください。
容器に直接口をつけて飲むと、口内の常在菌により水が汚染される恐れがあります。
仮にコップなどが無く、容器に口をつけて飲んだ場合は、その日のうちに使い切るようにしてください。
ローリングストック方式を取り入れる
ローリングストック方式とは、災害時の備蓄用品を日常から多めに確保しておき、それらを定期的に使用しながら、減った分をその都度追加していく方法です。
水道水を保存する場合も、保存容器に日にちをメモしておき、日数の経過したものから使用・その後新たにくみ置きする、という方法で備蓄するようにすると、日常生活のなかで効果的に、災害に備えることができます。
橋本市 上下水道部 水道施設課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-2861 ファクス:0736-32-8688
問い合わせフォーム




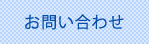
更新日:2024年08月13日