第1節 自然環境特性
1.地形・地質
本市の地形的特徴は、市域の中央部を紀の川が東から西に流れ、紀の川に沿って市街地、集落地が形成され、大きく北から和泉山地、橋本丘陵、紀の川段丘、紀の川低地となり、紀の川をはさんで、九度山山麓地、高野山地へと連なっています。
2.気候
気候は、降水量が比較的少なく、瀬戸内式気候の特性を有するものの、同気候帯では内陸部に位置することから、気温の高低差が大きいなど、やや内陸性の気候の特性も有しています。
3.水系
本市は、一級河川である紀の川を本流域に、橋本川、山田川、田原川、嵯峨谷川等を支流域とする河川流域で形成されています。
本流域である紀の川は、日本最多雨地帯として知られている大台ヶ原にその源を発し、紀伊半島を東西に流れ、紀伊水道へと注がれています。その流域の大半が、山地で占められており、奈良県から和歌山県にまたがる流域面積は1,750平方キロメートル、流路延長は136キロメートルとなっています。
4.植生
本市の植生は、市域北部の丘陵地及び南部の山地におけるスギ、ヒノキ、サワラ等の常緑針葉樹林と、中央部の水田雑草群落から構成されています。また、南部には、一部モチツツジ-アカマツ群落が見られるとともに、市全域にはコナラなどの広葉樹林も点在しています。
市域全体に占める林野率は、約60%であり、そのうち人工林が65%を占めています。
5.動物
本市における学術上価値の高い生物として、昭和40年代には、紀見峠周辺地区に、ギフチョウ、ナガボシカメムシ、フサヒゲサシガメ、ウラナミアカシジミなど県下で極めて少ないものが生息し、ハッチョウトンボの県下唯一の生息地との報告がありましたが、現在では、その数もさらに減少、あるいは絶滅したものと考えられます。
また、昭和56年発行の第2回自然環境保全基礎調査(環境庁)によると、指標昆虫類であるムカシトンボ、ムカシヤンマ、ハッチョウトンボ、ハルゼミの生息が、絶滅危惧種としてナニワトンボの生息が報告されています。
さらに、淡水魚類では、ニッポンバラタナゴ、アユカケ(カマキリ)、アブラハヤの生息が報告されているほか、哺乳類では、イノシシ、キツネ、タヌキが生息するという情報が得られています。
橋本市 総務部 生活環境課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム




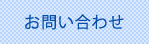
更新日:2013年02月28日