救急車の適正利用
救急車を効果的に運用するために適正な利用をお願いします。
救急業務とは
救急業務とは消防法第2条第9項で下記のように定められています。
「救急業務とは、災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故(以下この項において「災害による事故等という。)又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち、医療機関そ の他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によって、医療機関(厚生労働省令で定める医療機関をいう。)その他の場所に搬送すること(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急の手当を行うことを含む。)をいう。
救急業務とは、「ケガや急病で緊急に病院へ搬送の必要がある人を救急車で病院等へ搬送すること。」です。
救急体制について
救急車の出動
救急車の出動が多発したり、最寄の消防署の救急車が別の要請で先に出動している場合、必ずしも近くの救急車が出動するとは限りません。

救急講習の受講
傷病者の方の容体が悪く、呼吸が止まったり、脈拍が触れない場合などは、119番の通報時に指令センター員が応急処置の方法を電話で指示させていただくこともあります、日ごろから応急処置の方法を普通救命講習などで身につけるようにしましょう。

病院での診察
「救急車で病院に行けば待たずに診察してもらえる。」と思っている方もおられますが、救急車で病院に行っても症状によっては、外来診療の患者さんと同じように受付順の診察になる場合もあります。

救急車のサイレン
「サイレンを鳴らさないで来てください。」ということを言われることがありますが、緊急車両はサイレンを鳴らして、かつ、赤色灯を点灯して走行しなければならないと、法律で定められていますのでご承知ください。

こんな時は迷わず119番!!
- 反応(意識)がない
- 呼吸(息)をしていない
- 大量の出血がある
- 骨折して動けない
- 広範囲の熱傷(やけど)
- 持続する痙攣や、繰り返す痙攣

地図
橋本市消防本部 指令室
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-34-0119 ファクス:0736-33-0630
問い合わせフォーム




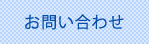
更新日:2025年12月05日