「クビアカツヤカミキリ」の侵入に注意!もも・うめなどの樹を食害します!
1. 発生状況
- 令和2年5月26日時点でかつらぎ町と岩出市での被害を確認していましたが、新たに橋本市において1園地2樹の被害を確認されました。また、令和2年6月9日時点で新たに紀の川市において、2園地4樹の被害を確認し、かつらぎ町及び岩出市で被害園と被害樹がともに増加しました。
- 橋本市で確認された箇所の近隣農地(1ha)を調査したところ、ほかの生態・フラス(木屑と虫糞が混じったもの)等は確認されませんでしたが、6月上中旬より成虫の羽化脱出が始まります。
- 本種の既発生地では分布が拡大しており、今後、橋本市内で分布が拡大する恐れがあります。
- 園地やその周辺で成虫やフラスを発見した場合は、市役所農林振興課や伊都振興局農業水産振興課・林務課等にご連絡いただくとともに、速やかな防除を行ってください。
2. 生態
- 成虫の体長は3~4cm。全体に光沢のある黒色で、前胸は明赤色。
- 1~3年1化性のカミキリムシ。
- 幼虫は樹木内部を食い荒らし、枯死させます。
- 幼虫は5~6月に最も摂食活動が盛んとなり、6月に蛹化し成虫は6~8月に出現します。成虫は、幹や樹皮の割れ目に産卵し、8~9日後には孵化します。
- さくら、うめ、もも、ざくろ、かき、オリーブ、やなぎ、こなら等多くの樹種に寄生します。
3. 被害の実例
- 幼虫食入孔より排出されるフラスはうどん状で、時間が経つと固くなります。この「うどん状フラス」がある場合、樹の中に幼虫がいる可能性が高くなります。
- 羽化した成虫が樹より脱出する際に排出される木屑は、おがくず状で固まりません。脱出孔は食入孔よりかなり大きく、扁平であることが多くあります。
- 食入部位(フラス排出部位)は、地表に現れた太い根から大人の身長程度までがほとんどですが、3m以上の高い場所に侵入されることもあります。
- 多数のカミキリムシが寄生し、樹の内部を食い荒らされると、樹勢が低下してやがて枯死します。

成虫(体長は28~37mm。光沢があり黒色で胸部(首部)が赤い)

幼虫が排出したフラス
4. クビアカツヤカミキリの防除対策
- 成虫は見つけ次第、捕殺してください。
- うどん状フラスがある食入孔を見つけたら、千枚通しや針金等の先端を曲げて食入孔に入れ、中にあるフラスをかき出してから、薬剤を注入してください。針金等が幼虫まで届く場合は、針金等で突き刺し殺虫するとより効果があります。
- 樹の株元から1~2m程度の高さまで4mm目合いのネットを巻き付け、羽化後の成虫がほかの樹に移動するのを防ぎます。ただし、ネットをかみ切ったり、隙間から脱出する場合もあるため、ネット設置後も見回りを行い、捕殺してください。
クビアカツヤカミキリの防除薬剤
| 薬剤名 | 作物名 | 適用害虫名 | 使用方法 | 使用時期 | 使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロビンフッド | うめ、おうとう、かき、かんきつ、なし、びわ、ぶどう、もも、りんご、マンゴー | カミキリムシ類 | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差込み噴射 | 収穫前日まで | 2回以内 |
| 果樹類(かんきつ、りんご、なし、びわ、もも、うめ、おうとう、ぶどう、かき、マンゴー、いちょう(種子)、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、食用つばき(種子)を除く) | |||||
| さくら | クミアカツヤカミキリ | - | 6回以内 | ||
| ベニカカミキリムシエアゾール | うめ、おうとう、かき、かんきつ、なし、びわ、ぶどう、もも、りんご、マンゴー | カミキリムシ類 | 収穫前日まで | 2回以内 | |
| 果樹類(かんきつ、りんご、なし、びわ、もも、うめ、おうとう、ぶどう、かき、マンゴー、いちょう(種子)、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、食用つばき(種子)を除く) | |||||
| さくら | クミアカツヤカミキリ | - | 6回以内 | ||
| バイオリサ・カミキリ | 果樹類 | カミキリムシ類 | 地際に近い主幹の分枝部分等にかける | 成虫発生初期 | - |
防除薬剤については以下も参照してください
フラス等を発見された場合は、下記までご連絡願います
- 和歌山県 環境生活部 環境政策局 環境生活総務課
自然環境室 (電話)073-441-2779
- 和歌山県 伊都振興局 農林水産振興部
農業水産振興課 (電話)0736-33-4930
林務課 (電話)0736-33-4911
- 和歌山県農作物病害虫防除所 (電話)0736-73-2274
橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム




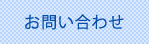
更新日:2020年07月10日